
「JFAバーモントカップ 全日本U-12フットサル選手権大会」(以下:バーモントカップ)は、公益財団法人日本サッカー協会(以下:JFA)が主催する、小学生年代のフットサル日本一を決定する大会です。
ハウス食品グループは、1998年の第7回大会から特別協賛という形でサポート。未来に大きな夢をもつ子どもたちを応援し続けています。
この大会の意義や「サッカーと食の力」について、さらには食やカレーライスにまつわるエピソードなどを、公益財団法人日本サッカー協会 会長の宮本恒靖さんとハウス食品グループ本社 取締役の佐久間淳さんに伺いました。
目次
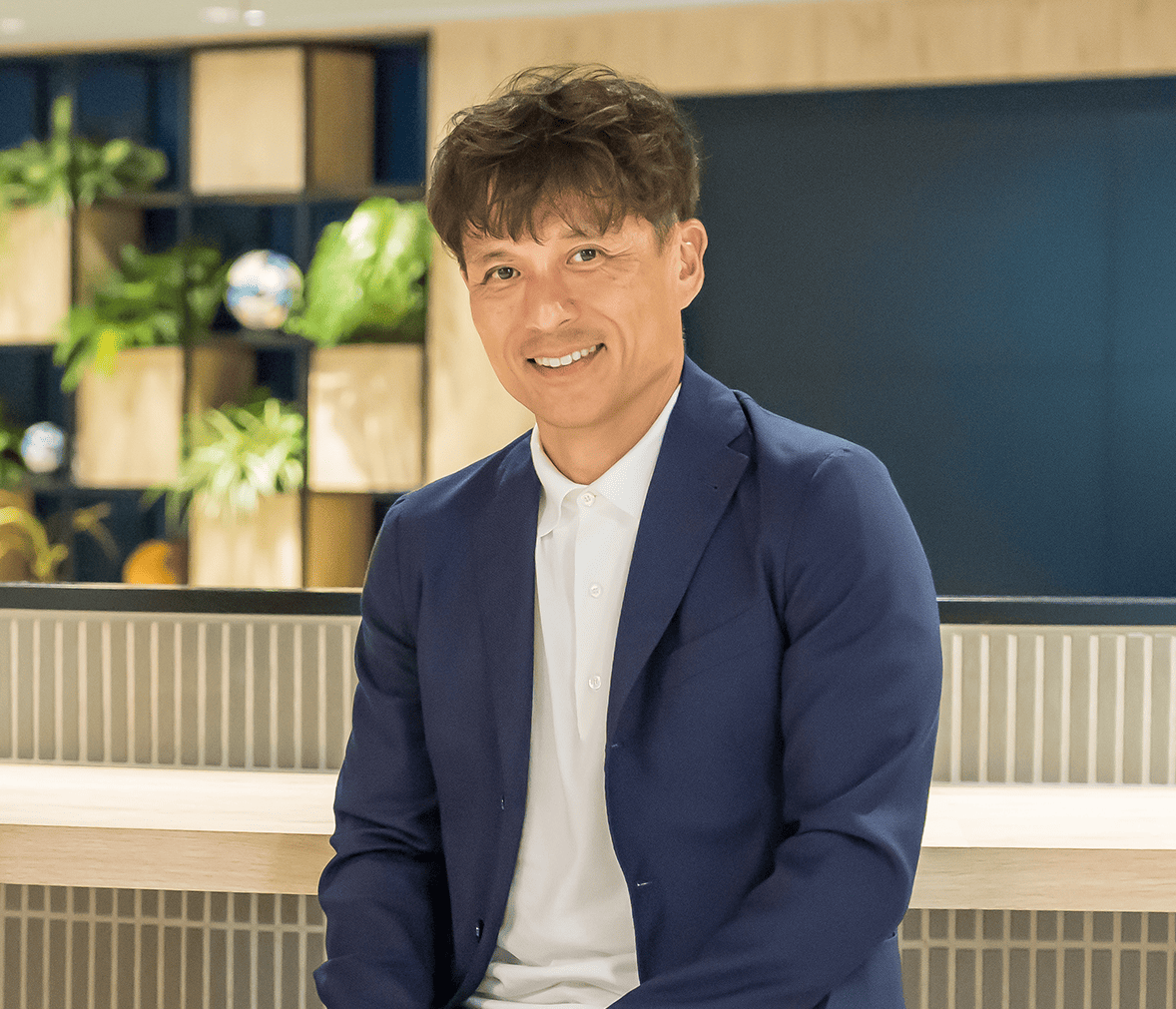
公益財団法人日本サッカー協会 宮本 恒靖(みやもと つねやす)
1995年ガンバ大阪入団。2007年よりレッドブル・ザルツブルク(オーストリア)、2009年よりヴィッセル神戸でディフェンダーとしてプレーし、2011年に現役引退。日本代表では長くキャプテンを務め、2002年日韓、2006年ドイツでのFIFAワールドカップに出場。引退後はガンバ大阪のU-23やトップチームの監督を務める。2024年3月、第15代日本サッカー協会会長に47歳の若さで就任。
外の空気を吸いながら汗を流すことがルーティーン。出張先でも5kmほどのランニングを欠かさない。
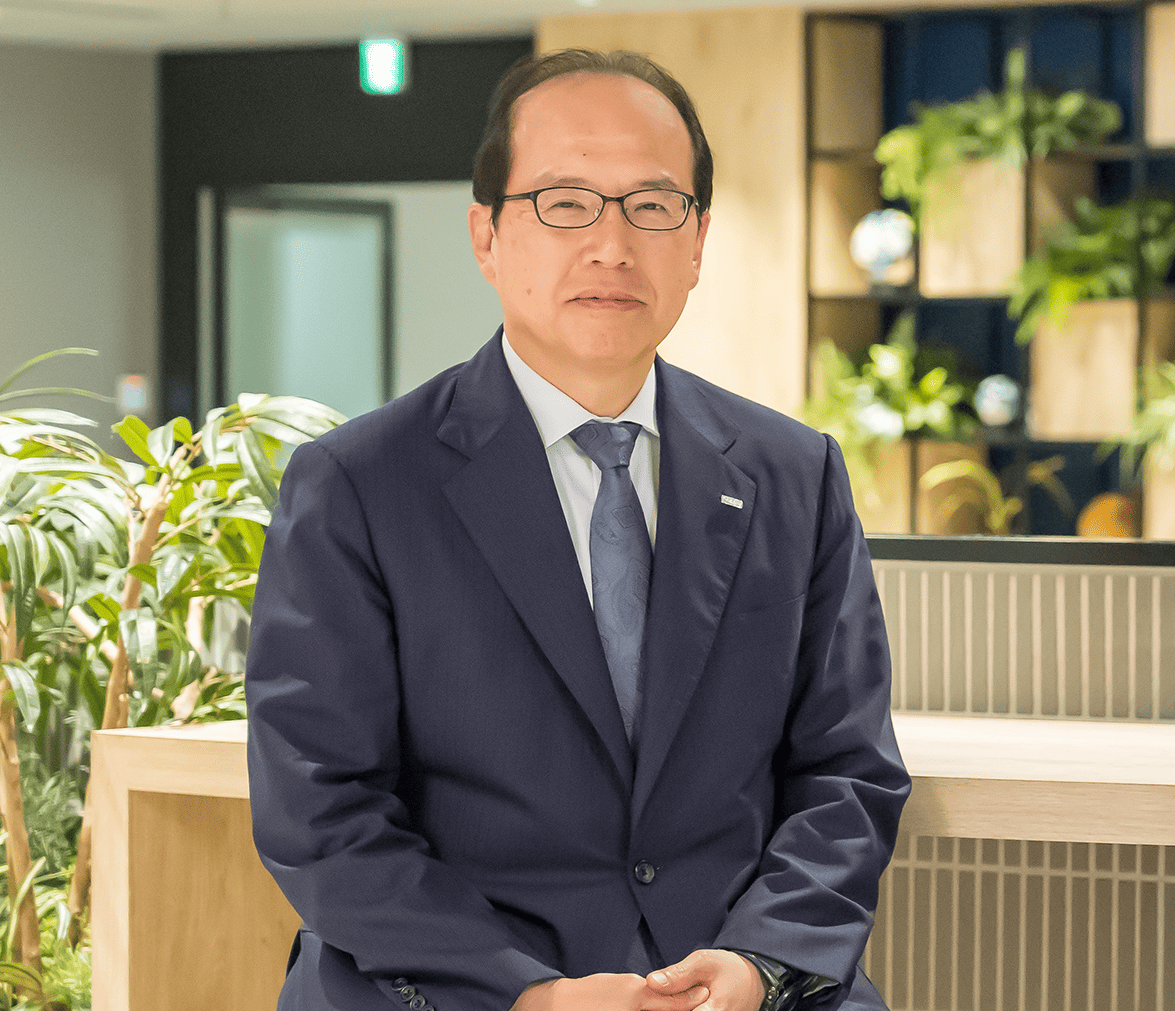
ハウス食品グループ本社株式会社 佐久間 淳(さくま あつし)
1989年ハウス食品入社。製品開発や食品事業の部長を経て、2023年より取締役に就任。コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部、国内関係会社事業推進部担当として、広告戦略や社会的課題の解決に向けた企業取組の推進、IT戦略の策定・推進、グループ各社の事業基盤拡大と強化に務める。趣味はカレーの名店を食べ歩くこと。多いときは1日に何軒もはしごするほどのカレー愛好家。

2025年8月の大会で第35回を迎える「バーモントカップ」。
毎年全国から集まった小学生が、日本一の座をかけて熱い戦いを繰り広げています。昨年は都道府県予選に2595チームが参加、勝ち抜いた48チームが夏の全国決勝大会に出場しました。
第1回大会に出場した小野伸二さんをはじめ、原口元気選手(浦和レッズ)、柴崎岳選手(鹿島アントラーズ)など、世界でも活躍した数々のトッププレーヤーを輩出しています。
小野伸二さんは沼津FCの一員として参加し、決勝で木暮賢一郎さん(現・名古屋オーシャンズ監督)のいる読売サッカークラブユースSに敗れたものの、準優勝。ご本人も優秀選手としてベスト5に選出されました。

――宮本さんからご覧になって、「バーモントカップ」はどのような意味をもつ大会か教えてください。
宮本:「バーモントカップ」には、全国各地から特徴のあるチームが集まります。小柄な選手が多いテクニカルなチームもあれば、大きな選手が主体でフィジカルを活かしてくるチームもあります。また、フットサル専門のチームや普段はサッカーをしているJリーグのU-12のチームも出場し、それぞれプレースタイルが異なります。「全国にはいろいろなチームがあるんだ」と、世間を知るような場になっているという意味で、小学生年代の選手にとって刺激になる大会だと思います。

宮本:昨年優勝したチーム(埼玉:戸塚FCジュニア)の中には、柏レイソルのジュニアユース(中学生)への入団が決まっている選手もいたと聞きました。「バーモントカップ」はみんなが目標にしている大会ですから、出場する選手はやはりレベルが高い。将来的にプロになれる可能性を秘めた選手たちが集まり、(小野)伸二のような選手が出てくるパスウェイの一つといえるのではないでしょうか。

佐久間:昨年、宮本さんやJFAの方たちと一緒に決勝を観戦しました。最後まで残った2チームの試合ですから、素人目線で見ても選手たちは本当に上手。小学生ながら戦術が決まっていて、それにのっとった組織的なサッカーをしていました。組織の攻防などがおもしろく、代表戦を見るときぐらい気持ちが入りました!
――小学生といっても、代表戦と同じような気持ちになるくらい、レベルが高い大会なのですね。
宮本:そうですね。少人数制のフットサルの大会ですが、パスでボールを動かしてスペースをつくり、そこに味方が走り込むといったグループ戦術を理解し、実際にできている印象を受けました。それは、11人制のサッカーをするうえでも役立つことです。
U-12の年代でフットサルをやることにも意味があります。狭いコートと少人数制によりボールに触れる回数が増えて、テクニックが身につくからです。U-12の年代というのは、年齢的にも神経系が一番発達する時期なんです。一度身についた技術を身体が覚え、何も考えず無意識にできるようになるんですよ。加えて、足の裏でボールコントロールをするのは、フットサル独特のテクニック。サッカーの場合は足の内側や外側でボールを止めることが多いのですが、フットサル経験者は大人になっても足の裏でボールを止める技術を発揮できるから、狭いスペースでもボールを上手く扱えるんです。

――JFAは、「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する」という理念を掲げていらっしゃいますが、サッカーを通じて、どのようなことを社会に提供したいとお考えになっているか教えてください。
宮本:我々が常に大切にしているのは、フェアプレイの精神や相手をリスペクトすることです。そういった価値観をサッカーを通して伝えていきたいと考えています。例えば最後の最後まで勝負を諦めない、チーム内で良いコミュニケーションをとるなど、そういったイメージ的なものも含めて、社会に、そして子どもたちに伝えていきたいです。
――そういった想いがJFAが掲げる「エンジョイ=スポーツの楽しさと喜びを原点にすること」、「プレーヤーズファースト=選手にとっての最善を考えること」、「フェア=オープンかつ誠実な姿勢で公正を貫くこと」、「チャレンジ=成長への高い志と情熱で挑戦を続けること」、「リスペクト=関わりのあるすべてを大切に思うこと」という5つのバリューに込められているのですね。

――では、宮本さんが感じる「サッカーの力」とはどんなところでしょうか?
宮本:「サッカーの力」を言葉にする際、いろいろな形容の仕方がありますけど、その中でサッカーには人を一つの方向にぐっと向かわせるような力があると思います。様々な世界大会での日本チームの活躍によるサッカーの盛り上がりで、国民の皆さんが一つになったと感じられました。WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)などもそうですけど、スポーツのうねり、盛り上がりには、そういうものを引き出す力がありますよね。
先ほど申し上げたフェアプレイやリスペクトの精神は、私自身がサッカーを通して学んできたもので、人として成長させてもらいました。それもやはりサッカー、スポーツがもつ力だと思います。

――ハウス食品グループの理念は「食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパートナーをめざします」ということですが、JFAとハウス食品グループの理念や活動で共通点を感じることなどはありますか?
佐久間:JFAさんの理念の中で、「人々の心身の健全な発達」が掲げられています。我々ハウス食品グループが扱う「食」には様々な機能がありますが、第一は「栄養」です。「栄養」は心と身体の健康には欠かせないもので、JFAさんの理念との親和性が高いと感じています。
子どもたちの成長や未来を築く取り組みについても共感しています。当社が毎年開催する「はじめてクッキング」教室は、幼稚園・保育園のお子さんたちがカレークッキングを体験する取り組みです。「はじめてクッキング」教室を通じて、子どもたちは食べること、作ることの楽しさや、料理を作ってくれる人への感謝、生産者や流通に関わる人とのつながりを学べます。

佐久間:大会名に冠した「バーモント」はハウス食品の『バーモントカレー』のことです。実は『バーモントカレー』が1963年に誕生するまで、一般的にカレーといえば辛い大人の食べ物だったんです。そのカレーを大人も子どもも一緒に食べられるように、辛さを抑え、りんごとハチミツでマイルドな甘口に仕上げたのが『バーモントカレー』です。まさに子どもを応援するブランドなので、バーモントカップの趣旨にマッチします。JFAさんの理念への共感性も含め、1998年の第7回大会から協賛させていただいております。

宮本:カレーは元々大人の食べ物だったのですね。まったく知りませんでした!佐久間さんがおっしゃったとおり、JFAの理念は、サッカーを通じて未来をつくることを念頭に置いています。ハウス食品グループさんの理念も端的にいえば、食の力で未来をつくることだと思います。サッカーと食を通じて明るい未来を創造しようとする点で、お互いのマインドは同じ方向を向いているのではないでしょうか。
佐久間:ありがとうございます。同じ方向を向いていると感じてくださっているのはうれしい限りです。JFAさんが掲げられている5つのバリュー、「エンジョイ」「プレーヤーズファースト」「フェア」「チャレンジ」「リスペクト」は、食や我々のビジネスにも置き換えることができます。エンジョイ=食べる・調理を楽しむ、プレーヤーズファースト=お客様に対して最善を考える、フェア=誠実かつ公正な事業に取り組む、チャレンジ=子どもたちの挑戦を応援する、リスペクト=生産者・食材などへの感謝を育む、といった具合です。分野は違えど、とても共通点の多いバリューですよね。サッカーや食を通じて、子どもたちをはじめ、みなさまの未来の笑顔を育むために、これからもJFAさんと一緒にお仕事をさせていただきたいと思う理由です。

――ハウス食品グループは、食を通じて子どもたちにどのようなことを伝えていきたいとお考えですか?
佐久間:「食」は身体的・精神的にも、子どもたちが成長していくためにとても重要だと考えています。バランスの良い食事や食べることの楽しさを伝えていきたい。そして、食を通じた人と人とのつながりも大切です。例えばカレーは1人で食べてもおいしいですけど、みんなと一緒に食べるともっとおいしいと感じられるじゃないですか。調理も同じで、「はじめてクッキング」の活動では、「みんなでカレーを作ると楽しい」と、大変喜ばれます。食には人と人をつなげ、みんなを幸せにする力があることを、メッセージとして届けたいと考えています。
――「バーモントカップ」の協賛や「はじめてクッキング」教室以外にも、ハウス食品グループの理念を具現化するような子どもに対しての取り組みはありますか?
佐久間:「食でつなぐ、人と笑顔を。」というメッセージを掲げ、「ファミリーウォーク」など、子どもたちの心身の成長のために取り組んでいる活動がたくさんあります。「はじめてクッキング」教室と「ファミリーウォーク」は、「バーモントカップ」の協賛と同様、約30年にわたる取り組みで、毎年多くの方たちに参加いただいています。また、子どもたちが初めてクラシック音楽にふれられる「ファミリーコンサート」に協賛しています。

佐久間:この他にも、子育てや仕事に忙しいご家庭を食で応援する『famimog(ファミモグ)』というプロジェクトや、子ども食堂への支援活動を行っています。当社オリジナルキャラクターのリンゴキッドを活用した食を楽しく学ぶためのコンテンツ(紙芝居・自由研究サイトなど)も展開しています。

――学童期(小学生)の子どもたちにとって、サッカーをすることで健康面や心の成長にどのように影響すると宮本さんはお考えでしょうか。
宮本:サッカーやフットサルに限らず、スポーツをすることで身体が鍛えられ、栄養を摂ることで肉体的な成長につながりますよね。また、運動することで疲れて眠くなりますから、夜しっかり睡眠(休養)がとれる。それで疲れが回復するのはもちろん、育ち盛りの子どもはより成長できます。ですから、スポーツを行うことで身体の成長に欠かせない正しい生活のリズムが身につけられると思います。
練習や試合では、上手くいくことばかりではありません。そのときに「くじけない」とか、「乗り越えるためにどうすればいいのか」といったことを自分で考えるようになるでしょう。スポーツを通して、そういったメンタル面についても子どもたちは学べると、常々思っています。

――宮本さんがサッカーを始めたのは小学校5年生とのことですが、当時の宮本さんの食生活について教えてください。
宮本:家で食べる食事がすべてでした。母は栄養バランスに気をつけながら食事を出してくれていたと思います。私自身は好き嫌いはまったくなく、いろいろなものを食べていました。肉とか魚だけでなく、野菜も食べていましたし、もちろん炭水化物も。当時はまだ食育という言葉はなかったですけど、「いろいろなものを食べることが成長するうえで大事だよ」という、母からのメッセージが毎日の食事に込められていたのかなと思います。
子どもの頃に好きだった料理はカレーやハンバーグかな。カレーは晩ごはんで食べたら、必ず翌朝も食べていました。“次の日のカレー”はちょっと煮込まれていて、おいしいじゃないですか。宮本家のカレーは、そんなに甘くなかったです。両親が辛いカレーが好きだったので、大人の味に姉と一緒に子どもながら、ついていったような気がします(笑)。

――子ども時代、食べる量は多かったのでしょうか?
宮本:成長期の頃はやはり多かったのですが、食べるタイミングがあまり良くなかったんです。高校生の時18時から2時間半くらい練習がありました。家が練習場から遠かったので、帰宅してご飯を食べるとなると22時過ぎになってしまうんです。本来、運動をした30分後くらいが食事を摂る適切なタイミングなんですが、物理的にできませんでした。それが自分の成長においては良くなかったと思うんです。その経験を踏まえて、現役を引退してジュニアユースのコーチになったときに、子どもたちにはそういった食事を摂るタイミングの大切さを伝えました。

――少年時代にお好きだったというカレーライスですが、現役時代もよく食べていましたか?
宮本:日本のカレーもインドカレーも、いろいろなカレーを食べてきました。オーストリアのザルツブルクでプレーした時期もカレーは食べていましたよ。自炊することもありましたし、家族が作ってくれることもありました。現場を離れた最近は、仕事で北海道に行くとスープカレーをよく食べています。バーモントカレーももちろん、食べたことがあります。いつから食べ始めたか記憶にないぐらい、テレビのCMも含めてすごく身近にあるものですよね。
佐久間:ありがとうございます。私からも一つ質問させてください。宮本さんが現役で世界を相手に戦っていた頃も西芳照さん(※)特製のカレーライスが試合後に振る舞われていたと聞いたのですが、それは本当ですか?
※数々のサッカー世界大会に帯同し、選手たちのコンディションを食事面からサポートしてきた料理人。

宮本:はい。試合会場から宿舎に戻ると必ずカレーが出ました。西さんのカレーは具材がゴロゴロ系のビーフカレーだったと記憶しています。試合後も、カレーを出すクラブは多いと思います。試合で疲れて食欲がわかないときでもカレーなら食べやすいんです。それに、カレーはたんぱく質や炭水化物などの栄養素をまとめて摂れるのが非常に大きなメリットです。特に夏場は試合後に体重が減ってしまうのですが、食べることで回復させないといけません。なので、カレーは選手みんなの定番の食事でしたね。
佐久間:カレーは香りがあってスパイスの力で食欲が増しますからね。ただ、それでもサッカー選手の試合中のハードワークは相当なものですよね。疲労感で食欲が出ないのかなと思っていたのですが、「試合後にカレーを食べました」とはっきり言っていただいて、すごくうれしいです!

――カレーは子どもの好きな料理ランキングでも常に上位にランクインしていますが、食品メーカーとしても、カレーは身体づくりに必要な栄養素などを効果的に摂れる料理としておすすめなのでしょうか?
佐久間:とてもおすすめの一品です。カレーはどんな具を入れても合いますし、主食・主菜・副菜を同時に食べられ、一皿で完結できます。カレーライス一皿には一食に必要なたんぱく質が多く含まれています。他にもビタミンD、ビタミンA、ビタミンK、ビタミンEという脂溶性ビタミンの吸収性がすごく良いのです。ビタミンDとKは骨の成長に関わる栄養素なので、育ち盛りの子どもにとって大切なものです。野菜嫌いな子でも「カレーに入っているにんじんや玉ねぎは食べられる」という声もよく聞きます。カレーライスは子どもの成長を助けるメニューであり、宮本さんがおっしゃったようにアスリートのリカバリーにも非常に適したメニューだと再認識しました。
――撮影で宮本さんに召し上がっていただいた「バーモントカレー」は、レトルトタイプなんですよね?
佐久間:はい。レトルトタイプは2023年から発売した商品です。「バーモントカレー」の歴史は60年以上あるのですが、レトルトカレーとして再現することが難しく、なかなか商品化できませんでした。「バーモントカレー」はカレーの中でも味わいが比較的穏やかなカレーのため、レトルト用に高熱をかけて殺菌すると香りや風味が飛んでしまうのです。そこで、新たな複数の原料とスパイスを組み合わせて焙煎する方法を導入し、500回以上の試作を行った結果、まろやかでコクのある「バーモントカレー」らしい味わいを再現できるようになりました。宮本さん、ちゃんと「バーモントカレー」の味になっていましたか!?

宮本:間違いなく「バーモントカレー」の味です!
佐久間:良かったです!(笑) レトルトなら時間がないときにでも、簡単に作れて手軽に食べられます。具として牛肉、じゃがいも、にんじんが入っていますので、お子様の身体づくりのお役に立てる製品として、ルウタイプ同様おすすめです。

――JFAの中期計画では、「キッズ、女子、シニア」を重点3領域とし、「関連団体とさらなる連携を図る」といったことも掲げられています。「バーモントカップ」は、そのどちらにも関わっていますが、サッカーを通じてスポーツ文化に対してどのようなビジョンをお持ちか教えてください。
宮本:子どもたちは “日本の未来”だと思いますし、子どもたちにサッカーやフットサルを通して、スポーツを楽しんでもらうことで健康になってもらいたいです。そしてスポーツ界を問わず、良い人材へと成長し、将来日本の社会を支えていってくれる子どもになってほしいと思います。
日本サッカーを強くするために、優秀な選手を生み出すことも重要ですが、一方で、競技者として上をめざしていく競争の中でサッカーを辞めてしまう、といった選手たちもいます。今後はプロサッカー選手をめざす育成のピラミッドとは別に、競技から離れてしまった選手でも、いつまでもサッカーを楽しんで続けてもらえるようなピラミッドをつくる“ダブルピラミッド”の考え方を、JFAは大事にしていきたいです。
現在、地域によってはO-80(80歳以上)のリーグ戦もあります。女子を含め、生涯にわたってプレーを楽しんでもらえるような環境づくりをめざしています。
――現在の「バーモントカップ」に対して感じている課題や、今後ハウス食品グループに期待することなどあれば教えてください。
宮本:いやいや、「課題」というのは特にありません。視察した大会では、良い雰囲気の中で良い内容の試合が続き、敗れた選手も賞賛すべきグッドルーザーでした。勝った選手は、様々な自信を身につけていく素晴らしい大会です。先ほど佐久間さんがお話しされたように、我々JFAのバリューがハウス食品グループさんと通ずる部分があるというのは、我々としても非常にありがたいです。日本の未来である子どものために、ぜひこれからもサポートしていただければ、というふうに思っています。
佐久間:ぜひ今後ともよろしくお願いします。宮本さんが会長に就任されて、日本のサッカー界はまた新しい未来が描かれています。その未来に向けて、「バーモントカップ」を通して少しでも協力させていただければ、我々としても大変ありがたいです。
――最後に、「バーモントカップ」全国決勝大会への出場をめざして、頑張る子どもたちへメッセージをお願いします。
宮本:練習ではたくさんボールに触って自分ができるプレーを増やし、自分がやりたいことを、どんどん試合の中で表現してみてください。そういった自分自身のチャレンジが、成功したときの喜びや、逆に上手くいかなかったときにどうすれば上手くいくのかを考えるきっかけになるでしょう。「バーモントカップ」をチャレンジする機会にしてほしいなと思います!

JFAは「アスパス!」(「地球(earth)の明日(未来)のために私たち(us)がつなぐパス」の意を込めた造語)という活動を通じて、社会貢献やSDGsの達成をめざし、全てのサッカーファミリーが世代や時代を超えてつながることを願っています。今回のインタビューを通じて、JFAのそうした想いや未来に向けたビジョン、そしてハウス食品グループが食を通じて子どもたちの未来を育むことをめざしていることを強く感じました。
子どもたち一人ひとりが、サッカーを楽しみながら成長していく姿は、日本の未来そのものです。今後も多くの子どもたちが夢や挑戦を胸に、自分らしい未来を切り拓いていくその一歩を、私たちも全力で応援していきたいと思います。
▼JFAバーモントカップ第35回全日本U-12フットサル選手権大会はこちら
2025年の「JFAバーモントカップ」は、8月15日(金)~17日(日)に東京 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館・屋内球技場にて決勝大会が開催されます。例年、元プロサッカー選手をはじめ特別ゲストを交えたエキシビションマッチも行われています。ぜひご来場、お待ちしています!

※本記事における「サッカー」とは、JFAの基本規則において、サッカー、フットサル、ビーチサッカー、その他関連競技を広義に指しています。
取材日:2025年6月
内容、所属等は取材時のものです
▶公益財団法人日本サッカー協会(JFA)
▶バーモントカップ|ハウス食品グループ本社
▶ハウス食品グループの笑顔をつなぐ活動
▶子育てパパ・ママを食で応援!famimog(ファミモグ)
文:小林智明
写真:片桐圭
編集:株式会社アーク・コミュニケーションズ
ホーム 食でつなぐ、人と笑顔を。 &House 【宮本恒靖×ハウス】JFAバーモントカップがつなぐ子どもたちの未来